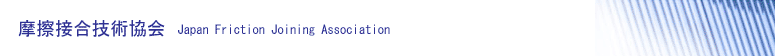
|
|
||
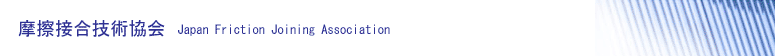 |
||
|
|
||
 2022,2023 年度本会会長を務めました福本です.コロナ禍の影響が残るなか,執行部役員,理事・監事各位初め皆様方のお力添えを頂きながら,規約および旅費規程等の改定,研究奨励賞の新設,各種表彰事業の実施,60 周年記念式典の開催初め,責務の一端を果たすことができました.ここに御礼申し上げます.この度 6 月 26 日開催の 2024 年度定時総会におきまして,改めて 2024,2025 年度会長の 指名を頂きました.新執行部として一丸となり責任感を持ち務めて参りますので,引き続き宜しくお願い申し上げます.
2022,2023 年度本会会長を務めました福本です.コロナ禍の影響が残るなか,執行部役員,理事・監事各位初め皆様方のお力添えを頂きながら,規約および旅費規程等の改定,研究奨励賞の新設,各種表彰事業の実施,60 周年記念式典の開催初め,責務の一端を果たすことができました.ここに御礼申し上げます.この度 6 月 26 日開催の 2024 年度定時総会におきまして,改めて 2024,2025 年度会長の 指名を頂きました.新執行部として一丸となり責任感を持ち務めて参りますので,引き続き宜しくお願い申し上げます.
本会は 1964 年に摩擦圧接技術の利用促進を目的に発足した摩擦圧接研究懇談会を遠源に,幾度かの会の名称変更を経た後,2012 年に摩擦接合技術協会として一般社団法人化し今日に至っています.端的に本会は「材料間の相対運動による摩擦発熱を援用した材料加工技術」を基盤とする国内唯一の由緒正しき学術団体であり,この独自技術の代表である摩擦圧接,摩擦攪拌接合等を駆使しながら,材料間界面の固相接合や固体表面への改質層形成の学理解明,固有技術のデータベース化及び社会実装化に向け,独自の活動を展開して参りました.初心忘るるべからずで,本会の原点は常にここに在ります.
この様な本会の独自性に鑑み私は,二年前の会長就任を機に本会基盤技術の高度化また会勢拡充に向け,五つの委員会体制・機能の構築を提案させて頂きました.今回新たな期の開始に当たりこれを拡充する形として以下の機能構築を引き続き志向して参りたいと存じます.
1.新技術の開拓:摩擦接合技術高度化のために,国内外の最新の技術情報を収集し,研究会活動への反映を通し会員各位に配信,還元<シーズの拡充>
2.技術応用先の探索:摩擦接合技術の実用・社会実装化に向け,ニーズを有する関連学協会や各種機関との連携推進,合同講演会の開催<シーズ・ニーズのマッチング>
3.規格の拡充:保有資産としての摩擦接合技術独自データベースの拡充,JIS, ISO 関連情報のキャッチアップ<シーズスタンダード化>
4.編集出版広報の拡充:協会誌の発刊,書籍の出版,独自技術の対外アピール,協会 HP の刷新など<ブランディング>
5.記念事業の準備:70 周年記念事業に向けた準備に着手
以上の各項目は地区担当副会長を主査とし,主査指名の数名の理事各位にも分担して頂く総力での取り組みを目指します.
人口減少とともに国際社会における相対的国力の減退し続ける我が国にあって,老舗とも言われる大規模な国内学協会の多くにおいて会員数の減少に歯止めがかからない状況が散見されます.これに対し当会は,小規模ながら新会員の参入にも恵まれ何とか会勢を維持できています.当会組織の基本構成単位が関東,中部,関西の3地区にあることを踏まえれば,今後は地区内会員間交流の実質化を通し地区組織の基盤形成と強化,活性化を進めることが肝要と考えます.地区担当副会長を中心に理事,会員各位が心を合わせ,地区の特色を活かした独自研究会,見学会,交流会等の開催を通じ,一丸となり当会会勢の更なる維持発展に向けご尽力頂けます様,引き続き宜しくお願い申し上げます.
| CopyRight©2008 Japan Friction Joining Association. All Rights Reserved. |
| トップページに戻る |